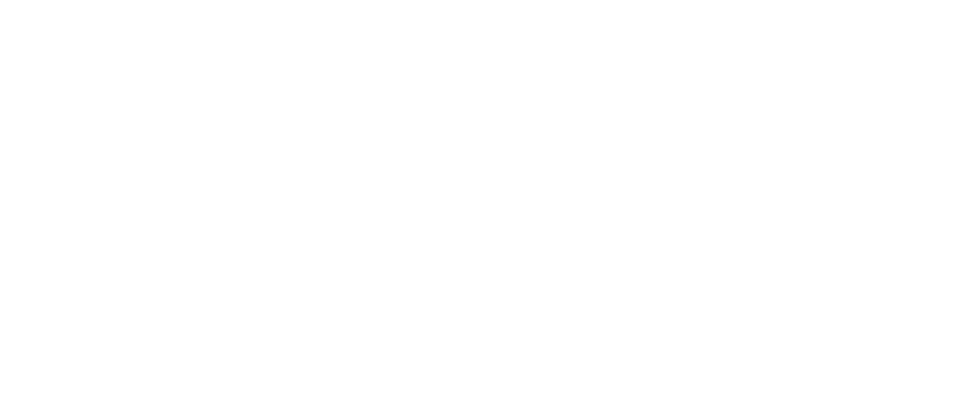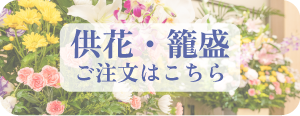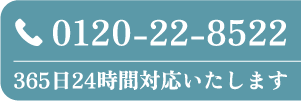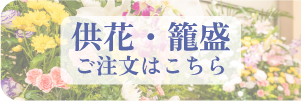互助会の解約手数料はいくら?
納得できないときの対処法も紹介
葬儀などの費用を前払いで積み立てる「互助会」は、いざ解約しようとすると思ったより返金が少ないと驚く方が少なくありません。その原因の一つが「解約手数料」です。

本記事では、互助会解約時にかかる手数料の相場や発生する理由、契約前に確認しておきたいポイント、納得できない場合の対処法や相談先まで、トラブルを避けるために必要な情報を詳しく解説します。
互助会とは?解約時に手数料が発生する理由
互助会とは、将来の葬儀や結婚式などのサービスを受けるため、月々の積立金を払って備える制度です。しかし途中で解約する場合、多くの互助会では「解約手数料」が発生します。
これは単なる違約金ではなく、これまでの事務手続き・運営管理にかかったコストとして規約に基づいて設定されています。契約時にしっかり説明されるべき内容ですが、実際には不十分な説明しかない場合も少なくありません。
解約手数料の相場|どのくらい差し引かれるのか?
互助会の解約手数料は、「支払済金額の10〜20%程度」が一般的な目安とされています。たとえば30万円積み立てた場合、3〜6万円程度が差し引かれて返金されることになります。
ただし、加入からの経過年数やプランの種類、運営会社の規定によって異なり、早期解約の場合は戻ってくる金額がごくわずか、またはゼロになるケースもあります。具体的な金額や返金率は契約書をよく確認し、できればシミュレーションしておくのが安心です。
契約書や規約で確認すべきポイント
解約手数料の算出方法や返金額については、契約書や重要事項説明書に記載されているのが一般的です。確認すべき主なポイントは以下の通りです:
- 解約が可能かどうか
- 解約時の返金額の計算方法
- 手数料の金額または率
- 解約による違約金の有無
もし不明点があれば、契約先に問い合わせて説明を受けましょう。後から「知らなかった」とならないよう、署名前にしっかり目を通すことが重要です。
「説明がなかった」「高すぎる」と感じたときの対処法
解約手数料が想像以上に高く、事前の説明もなかったという場合には、以下の対応を順を追って行うのがおすすめです。
最初のステップは、直接契約した互助会の運営会社に連絡を取って、解約手数料の詳細や計算根拠を改めて説明してもらうことです。
- どのような規約に基づいて手数料が算出されたのか?
- 事前説明がなかった場合は、なぜ説明されなかったのか?
- 書面や契約書にその内容が明示されているか?
この段階で、担当者に誠実な対応を求め、疑問点や不明点は遠慮せずに質問しましょう。
口頭でのやり取りだけでは、後々トラブルが長引く原因となるため、「解約手数料の内訳や規約を明示した書面の提出」を求めるのが有効です。
メールや文書で説明を受けることで、証拠として残せる
書面での説明を求めることで、運営会社の対応の誠実さも確認できる
もしも書面での提出を拒否されたり、対応が曖昧な場合は、次の段階に進みましょう。

運営会社との交渉で納得できない場合は、地域の消費生活センターや全国の国民生活センターに相談することをおすすめします。
相談時には、契約書ややり取りの記録、手数料の説明に関する書面など、可能な限り資料を揃えておくとスムーズです。
手数料が非常に高額で不当と思われる場合や、運営会社との話し合いが進まない場合は、法律の専門家である弁護士に相談することも選択肢です。
弁護士費用がかかりますが、高額な損失を防ぐ意味では検討の価値があります。
解約手数料に関するトラブルの実例
互助会の解約を巡っては、事前の説明不足や不明瞭な返金条件をめぐって、消費生活センターなどへの相談があとを絶ちません。ここでは、実際にあったトラブル事例を3つ紹介します。
事例①:全額返金されると思っていたが、5万円しか戻らなかった
 70代男性
70代男性母親の葬儀のために加入していた互助会を解約しようとしたところ、「すでにサービスを一部提供済み」との理由で、30万円以上積み立てたうち返金されたのはわずか5万円だった。
契約書に細かい記載はあったが、加入時に「将来必要なくなったら返金できる」としか説明されておらず、不満を感じて消費生活センターに相談。
事例②:高齢の親が知らないうちに契約、子どもが内容を把握していなかった



80代の母親が営業訪問を受け、互助会に加入。本人は契約内容を十分理解しておらず、亡くなったあとに私が解約手続きをしたが、「早期解約扱い」となり大半が手数料として差し引かれた。本人が認知症の傾向にあったため、家族として納得できず、弁護士を通じて交渉することに。
事例③:「手数料はかからない」と言われていたが実際には10万円差し引かれた
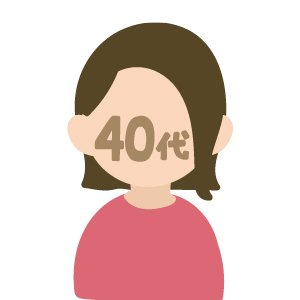
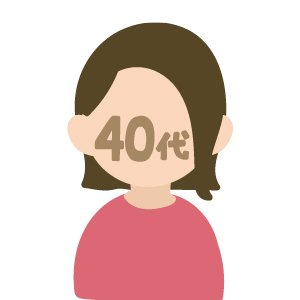
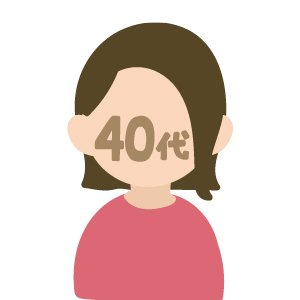
加入から5年で解約。営業担当者からは「もし解約しても元本は戻りますよ」と説明されていたが、実際には手数料として10万円が差し引かれた。その後、会社に確認したところ「契約書に書いてある通り」と一方的な対応をされたため、不誠実な説明として苦情を申し立て。
トラブルを避けるためにできること
互助会はうまく活用すれば安心材料になりますが、内容を十分に理解せずに契約すると、後々「こんなはずじゃなかった…」というトラブルにつながることも。ここでは、事前にできる予防策を具体的に紹介します。
契約前に規約と手数料を確認する
契約書や重要事項説明書に記載された「解約条件」「返金額の算出方法」「解約手数料の割合や金額」は、必ず事前に確認しましょう。「返金されますよ」「必要なくなれば解約できます」といったあいまいな表現に惑わされず、文書で具体的にどうなるのかを把握しておくことが大切です。
「元本保証かどうか」「解約の際にサービス提供済みとして差し引かれる可能性があるか」なども確認しましょう。
口頭だけでなく書面で説明を受ける
営業担当者の説明が丁寧だったとしても、口頭の説明だけでは証拠になりません。後から「言った・言わない」のトラブルになることを避けるために、「解約時の返金額の目安」や「手数料がかかるケースとかからないケース」などを、できるだけ書面で確認し、控えとして手元に残しておきましょう。不明点はその場でメモを取り、後日メールなどで再確認すると安心です。
家族と情報を共有する
加入者本人だけでなく、家族とも契約内容を共有しておくことが非常に重要です。とくに高齢の方が加入している場合、家族が知らずに解約を進めると「早期解約扱い」になるなど、思わぬ返金トラブルに発展することもあります。
契約書のコピーを家族に預けておく、家族同席で説明を受けるなど、家族ぐるみの情報管理を意識しましょう。
加入後も定期的に内容を見直す
加入当時は納得していた内容でも、年数が経つと制度変更やサービス内容の改定がある場合もあります。毎年1回でも見直す習慣を持つと、必要がなくなったときにスムーズに対処できます。
利用予定がなくなったら早めに見直し、無駄な積立を避けるのが得策です。
まとめ|納得できる形で解約手続きを進めよう
互助会の解約手数料は制度上発生するものであり、完全に避けることは難しい場合もあります。
しかし、「なぜこの金額になるのか」「説明は十分だったのか」を確認することで、納得感のある対応ができるはずです。疑問が残る場合は遠慮せず第三者機関に相談し、必要に応じて法的な対応も視野に入れましょう。
冷静に、丁寧に対応することが、トラブルを避けるカギとなります。
もしご不安な点がある場合は、お気軽にひびきセレモニーまでご相談ください。
お問い合わせ
ひびきセレモニーでは、
無料で事前相談を承っております。
まずはお電話、お問い合わせフォーム、
LINEからお気軽にお問い合わせください。
担当者より折り返しご連絡いたします。
0120-228-522
365日24時間対応 / 深夜早朝問わずご相談可能